�@�����^�l�H�q���p�����@�̃��x���_�C���O����
�A�c�v�����N�ƃ_�E�������N�e�X�̃��x���_�C���O�����ł��B(PDF�t�@�C��)
���j
1.���̐}�ɂ́A���L�̕s���m�ȂƂ��낪����܂��B
�@145MHz��M�@��IF AMP�o�͂́AIC(TA31188)�����Ō��g��H�ɒ��ڐڑ�����Ă��ĊO���ɏo�Ă��炸
�d�l���ɂ����L����Ă��Ȃ��̂ŁA�����l�ł��B
���g�o�͂�140mVrms��IC�̎d�l���ɏ�����Ă��邪�A�C���s�[�_���X�͕s���ł��B
�}�ł̓C���s�[�_���X��50���ł�����̂Ƃ��āA�v�Z�����Ă��܂��B
�o�͂̃I�y�A���v�́A-16dBV�̒l�ɂ��܂����B
������50���ł�����̂Ƃ��Ă̓d�͌v�Z�l�ł��B
�@�܂�IF AMP�ȍ~�́A���ۂ̃C���s�[�_���X�����āA�d�������ɒ��ڂ����}�ł��̂ŁA�^��
�d�̓��x���͈�����l�ɂȂ�܂��B
�������ꂽFSK�o�̓��x���́A����-16dBV�ɗ}�����ăn�C�C���s�[�_���X�̕��ׂƂȂ��Ă���B
2.SG(�W���M��������)�̏o�͓d���\��
�@�̂�SG�͐ݒ肵���o�͓d���̕\�����A�����Ă��J���[�d���ɂȂ��Ă���(�������̓d���\��)�B
SG���g���đ��肷�鐫�\�̋K�i���A�J���[�d���\���Ɋ�Â��Ē�߂��Ă���ꍇ�����������B
�������A���ݍ���Ă���SG�́A�I�[�����̓d���\���������A�ؑւ��\���o����^�C�v������B
����̂́A�I�[���דd���\���ɂȂ��Ă��܂��B
�@�Ⴆ�A�o�͓d���P��V��0dB/��V(���L=0dB��)�Ƃ��ĕ\�����Ă���ꍇ
�I�[���דd���\����SG�ł́A��������2��V(=6dB/��V)�A50�����ׂ�ڑ�����1��V(=0dB/��V)��
�o�͂����B(�I�[���דd���\����SG�ł́A0dB/��V=-107dBm�ł���)
�J���[�d���\��(EMF)��SG�ł́A��������1��V(=0dB/��V)�A50�����ׂ�ڑ���0.5��V(=-6dB/��V)
���o�͂����B(�J���[�d���\����SG�ł́A0dB/��V�ݒ莞�́A-113dBm�o�͂ɑ�������)
�@�������u�̐��\�𑪒肷�鎞�ɂ͎g�p����SG���ǂ���̕\���ł��邩���Ă����Ȃ��ƁA6dB�̑���
�덷�������Ă��܂��������邩��A���ӂ��K�v�ł���B
�@dBm�\���̏ꍇ�́A�I�[���דd���\���ŁA0dB/��V=-107dBm�̊W�����藧�悤�ɂ��Ă���悤
�Ȃ̂ŁA���̊ԈႢ�����邱�Ƃ͏��Ȃ��B
�g�p����SG���ǂ���̕\�����悭������Ȃ��ꍇ�́A�X�y�N�g���A�i���C�U�Ń��j�^���Ċm�F����
�Ɨǂ��B(107dB�ʂɏo�͐ݒ肵��0dBm�o�Ă��邩�ǂ����Ŕ��ʂ���)
��EMF�Ƃ́AElectro Motive Force�̗��ŋN�d�͡�M��������Ȃǂ̊J���[�̓d���\�����Ӗ�����
�@�@(�p��W������p)
3.�����g�����g�����W�X�^ 2SC3356
�@�g�����W�X�^2SC3356�𑽗p���Ă��邪�A���[�m�C�Y(NF=1.1dB)��Ft=7GHz�A5V�ȉ��̒�d���ł�
�����悭���삵�Ă���āA�g���₷���f�q�ł���B
���M���������璆�M�������A����g����UHF�т܂ł̔��U�p�ȂǁA���̉�H�Ɏg�p�\�ł���B
���ɂ́A4�p�������ɂ���300mW(430MHz)���M�o�͂��o���g�����V�[�o�̗������B
�@�@(1������75mW�̑��M�o�͂ł���)
�@����̎�M�@�ŃA���e�i��������Ă����ɍ����g��������g�����W�X�^��2SC3356���g���Ă���B
�R���N�^�d�����[�������āA���o�͂̃C���s�[�_���X�}�b�`���O�����܂����킹��ƁA������20dB
���x����B
�������A���̏�Ԃɂ���ƃA���e�i��SWR���ǂ��Ȃ�����A�A���e�i���O��Ă��鎞�Ɉُ픭�U����
���ۂ��������č��邱�Ƃ�����B
�@����́A����d�������Ȃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA3mA���x�ɃR���N�^�d����}���Ă��邩��A
�����͏��Ȗڂł���B
����ł��A�A���e�i�̏�Ԃɂ���ẮA�ُ픭�U����ꍇ��������̂ŁA�R���N�^�֒����
���U�~�߂̒�R(R2,150��)�����āA���x�������Ȃ�Ȃ����x�ɗ����������Ĉ��艻�����B
�@�����g�����i�́A�A���e�i���ُ�ł����Ă��A���ُ̈픭�U���N�����Ȃ��悤�ɂ��鎖���d�v�ŁA
���̐��A�����ł̗�������ɂ����đ傫���v�f�ɂȂ�A���O�̌v�Z������B
���i�z�u�E��p�^�[�����̉e�����傫���A���тɂ��o���Ɗ��ɗ���Ƃ���ł���B
�܂�A�����f�q�̔\�͂��A���Ȃ��߂̗����ɉ����Ďg�p���Ȃ��ƕs����ɂȂ�ꍇ�������A
�O��ɐڑ�������H�̏�ԂōœK�l�͕ς���Ă���B����̂́A��10dB�̗����Ɛ��肳���B
(���M�̏I�i�d�͑������A���e�i�̏�Ԃňُ픭�U���ɂ����悤�ɂ���ׂɌ������]���ɂȂ�)
4.�����g���ϊ���H(1st Mixer)
�@���g���ϊ���H(MIX)�ɂ�L6��C12�̒���f�q��2SC3356�̃x�[�X��GND�Ԃɂ��邪�A����͊Ԉ�
���ł͖����A�C���s�[�_���X�}�b�`���O�ł͖��ʂȉ�H�f�q�ł��邪�A�ʂɑ傫���Ӗ�������B
����2�̑f�q(L6��C12)��lj�����ƁA���x���ǂ��Ȃ�A�����������I��x�����P�����B
���̌��ʂ͖��炩�ɑ傫���̂ł��邪�A�Ȃ�����发�ɂ����̓_�ɂ��Ă̋L�q���������������B
����́A�u���g���ϊ����Ď��o�����Ƃ���ړI��IF���g���v�Ɓu2�M�����̖W�Q�g�r�[�g���g���v
�ɑ��āA�x�[�X�̃C���s�[�_���X��Ⴍ���Ă��ƁA�ϊ��������オ������I��x�����P�����A
�Ƃ������ۂł��邪�A���̓_�̗��_�I�ȗ��t���͂悭������Ȃ��B
�O�ɁA�����d���Ő��\�̗ǂ����g���ϊ���H���������Ă����Ƃ��ɁA��������R���������B
���܂����������12dBSINAD,-3dB,3�M���@�ŗאڥ���אږW�Q�ɂ����āA70dB������ꂽ��������B
�]���āADBM��FET���g���������\�ȉ�H�ɋ߂����\��������B
�ǂȂ����A���̓_�ɂ��ė��_�I�ɕ���������܂����狳���ĉ������B
�@�g�����W�X�^�ɂ����g���ϊ���H�́AFET��DBM�������I��x���ǂ��Ȃ��ƌ�����B
����A����d�������Ȃ��A�ǔ����x�����������čς݁A�S�̂Ƃ��ď��^���o����Ƃ�������������B
L6��C12�̒���f�q�́A���̗ǂ��_�����Ȃ���A�����I��x���ǂ�����m�E�n�E�ł���B
���ʂ́A���^�Œ����d���̊��ɂ͍����x�ł�������I��x���ǂ��A�o�����X�ǂ���H���o����B
�@PLL IC�̒��ɂ́A��M�p�̎��g���ϊ���H����������Ă��邪�A����͎g��Ȃ������B
�ȑO�A������g�������ɁA�����M������M�����PLL��H�Ɏ�M�M������荞��ŁA���삪�ُ��
�Ȃ錻�ۂ��������B(�ʏ�̓����Ԃł͖�薳����)
�_�E�������N�Ɠ����ɑ���M����\��������̂ƁA�����������͑���̑��M�@�Ƃ̋������߂��āA
���͂Ȏ�M�M���̂��ƂŎ��������ꍇ�������Ǝv����̂ŁA������g��Ȃ����Ƃ����B
�@�{���́A���������Ȃ���f�ڂ��Ă���̂ŁA�܂����������������������邪�A��e�͊肢�܂��B
���ӌ��E���₢���킹�����[���͂������
�������������� HOME��
-----�ҏW�ӔC�ҁF�� �T�� (Ji3CKA)-----
�@
�@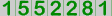
�A�c�v�����N�ƃ_�E�������N�e�X�̃��x���_�C���O�����ł��B(PDF�t�@�C��)
���j
1.���̐}�ɂ́A���L�̕s���m�ȂƂ��낪����܂��B
�@145MHz��M�@��IF AMP�o�͂́AIC(TA31188)�����Ō��g��H�ɒ��ڐڑ�����Ă��ĊO���ɏo�Ă��炸
�d�l���ɂ����L����Ă��Ȃ��̂ŁA�����l�ł��B
���g�o�͂�140mVrms��IC�̎d�l���ɏ�����Ă��邪�A�C���s�[�_���X�͕s���ł��B
�}�ł̓C���s�[�_���X��50���ł�����̂Ƃ��āA�v�Z�����Ă��܂��B
�o�͂̃I�y�A���v�́A-16dBV�̒l�ɂ��܂����B
������50���ł�����̂Ƃ��Ă̓d�͌v�Z�l�ł��B
�@�܂�IF AMP�ȍ~�́A���ۂ̃C���s�[�_���X�����āA�d�������ɒ��ڂ����}�ł��̂ŁA�^��
�d�̓��x���͈�����l�ɂȂ�܂��B
�������ꂽFSK�o�̓��x���́A����-16dBV�ɗ}�����ăn�C�C���s�[�_���X�̕��ׂƂȂ��Ă���B
2.SG(�W���M��������)�̏o�͓d���\��
�@�̂�SG�͐ݒ肵���o�͓d���̕\�����A�����Ă��J���[�d���ɂȂ��Ă���(�������̓d���\��)�B
SG���g���đ��肷�鐫�\�̋K�i���A�J���[�d���\���Ɋ�Â��Ē�߂��Ă���ꍇ�����������B
�������A���ݍ���Ă���SG�́A�I�[�����̓d���\���������A�ؑւ��\���o����^�C�v������B
����̂́A�I�[���דd���\���ɂȂ��Ă��܂��B
�@�Ⴆ�A�o�͓d���P��V��0dB/��V(���L=0dB��)�Ƃ��ĕ\�����Ă���ꍇ
�I�[���דd���\����SG�ł́A��������2��V(=6dB/��V)�A50�����ׂ�ڑ�����1��V(=0dB/��V)��
�o�͂����B(�I�[���דd���\����SG�ł́A0dB/��V=-107dBm�ł���)
�J���[�d���\��(EMF)��SG�ł́A��������1��V(=0dB/��V)�A50�����ׂ�ڑ���0.5��V(=-6dB/��V)
���o�͂����B(�J���[�d���\����SG�ł́A0dB/��V�ݒ莞�́A-113dBm�o�͂ɑ�������)
�@�������u�̐��\�𑪒肷�鎞�ɂ͎g�p����SG���ǂ���̕\���ł��邩���Ă����Ȃ��ƁA6dB�̑���
�덷�������Ă��܂��������邩��A���ӂ��K�v�ł���B
�@dBm�\���̏ꍇ�́A�I�[���דd���\���ŁA0dB/��V=-107dBm�̊W�����藧�悤�ɂ��Ă���悤
�Ȃ̂ŁA���̊ԈႢ�����邱�Ƃ͏��Ȃ��B
�g�p����SG���ǂ���̕\�����悭������Ȃ��ꍇ�́A�X�y�N�g���A�i���C�U�Ń��j�^���Ċm�F����
�Ɨǂ��B(107dB�ʂɏo�͐ݒ肵��0dBm�o�Ă��邩�ǂ����Ŕ��ʂ���)
��EMF�Ƃ́AElectro Motive Force�̗��ŋN�d�͡�M��������Ȃǂ̊J���[�̓d���\�����Ӗ�����
�@�@(�p��W������p)
3.�����g�����g�����W�X�^ 2SC3356
�@�g�����W�X�^2SC3356�𑽗p���Ă��邪�A���[�m�C�Y(NF=1.1dB)��Ft=7GHz�A5V�ȉ��̒�d���ł�
�����悭���삵�Ă���āA�g���₷���f�q�ł���B
���M���������璆�M�������A����g����UHF�т܂ł̔��U�p�ȂǁA���̉�H�Ɏg�p�\�ł���B
���ɂ́A4�p�������ɂ���300mW(430MHz)���M�o�͂��o���g�����V�[�o�̗������B
�@�@(1������75mW�̑��M�o�͂ł���)
�@����̎�M�@�ŃA���e�i��������Ă����ɍ����g��������g�����W�X�^��2SC3356���g���Ă���B
�R���N�^�d�����[�������āA���o�͂̃C���s�[�_���X�}�b�`���O�����܂����킹��ƁA������20dB
���x����B
�������A���̏�Ԃɂ���ƃA���e�i��SWR���ǂ��Ȃ�����A�A���e�i���O��Ă��鎞�Ɉُ픭�U����
���ۂ��������č��邱�Ƃ�����B
�@����́A����d�������Ȃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA3mA���x�ɃR���N�^�d����}���Ă��邩��A
�����͏��Ȗڂł���B
����ł��A�A���e�i�̏�Ԃɂ���ẮA�ُ픭�U����ꍇ��������̂ŁA�R���N�^�֒����
���U�~�߂̒�R(R2,150��)�����āA���x�������Ȃ�Ȃ����x�ɗ����������Ĉ��艻�����B
�@�����g�����i�́A�A���e�i���ُ�ł����Ă��A���ُ̈픭�U���N�����Ȃ��悤�ɂ��鎖���d�v�ŁA
���̐��A�����ł̗�������ɂ����đ傫���v�f�ɂȂ�A���O�̌v�Z������B
���i�z�u�E��p�^�[�����̉e�����傫���A���тɂ��o���Ɗ��ɗ���Ƃ���ł���B
�܂�A�����f�q�̔\�͂��A���Ȃ��߂̗����ɉ����Ďg�p���Ȃ��ƕs����ɂȂ�ꍇ�������A
�O��ɐڑ�������H�̏�ԂōœK�l�͕ς���Ă���B����̂́A��10dB�̗����Ɛ��肳���B
(���M�̏I�i�d�͑������A���e�i�̏�Ԃňُ픭�U���ɂ����悤�ɂ���ׂɌ������]���ɂȂ�)
4.�����g���ϊ���H(1st Mixer)
�@���g���ϊ���H(MIX)�ɂ�L6��C12�̒���f�q��2SC3356�̃x�[�X��GND�Ԃɂ��邪�A����͊Ԉ�
���ł͖����A�C���s�[�_���X�}�b�`���O�ł͖��ʂȉ�H�f�q�ł��邪�A�ʂɑ傫���Ӗ�������B
����2�̑f�q(L6��C12)��lj�����ƁA���x���ǂ��Ȃ�A�����������I��x�����P�����B
���̌��ʂ͖��炩�ɑ傫���̂ł��邪�A�Ȃ�����发�ɂ����̓_�ɂ��Ă̋L�q���������������B
����́A�u���g���ϊ����Ď��o�����Ƃ���ړI��IF���g���v�Ɓu2�M�����̖W�Q�g�r�[�g���g���v
�ɑ��āA�x�[�X�̃C���s�[�_���X��Ⴍ���Ă��ƁA�ϊ��������オ������I��x�����P�����A
�Ƃ������ۂł��邪�A���̓_�̗��_�I�ȗ��t���͂悭������Ȃ��B
�O�ɁA�����d���Ő��\�̗ǂ����g���ϊ���H���������Ă����Ƃ��ɁA��������R���������B
���܂����������12dBSINAD,-3dB,3�M���@�ŗאڥ���אږW�Q�ɂ����āA70dB������ꂽ��������B
�]���āADBM��FET���g���������\�ȉ�H�ɋ߂����\��������B
�ǂȂ����A���̓_�ɂ��ė��_�I�ɕ���������܂����狳���ĉ������B
�@�g�����W�X�^�ɂ����g���ϊ���H�́AFET��DBM�������I��x���ǂ��Ȃ��ƌ�����B
����A����d�������Ȃ��A�ǔ����x�����������čς݁A�S�̂Ƃ��ď��^���o����Ƃ�������������B
L6��C12�̒���f�q�́A���̗ǂ��_�����Ȃ���A�����I��x���ǂ�����m�E�n�E�ł���B
���ʂ́A���^�Œ����d���̊��ɂ͍����x�ł�������I��x���ǂ��A�o�����X�ǂ���H���o����B
�@PLL IC�̒��ɂ́A��M�p�̎��g���ϊ���H����������Ă��邪�A����͎g��Ȃ������B
�ȑO�A������g�������ɁA�����M������M�����PLL��H�Ɏ�M�M������荞��ŁA���삪�ُ��
�Ȃ錻�ۂ��������B(�ʏ�̓����Ԃł͖�薳����)
�_�E�������N�Ɠ����ɑ���M����\��������̂ƁA�����������͑���̑��M�@�Ƃ̋������߂��āA
���͂Ȏ�M�M���̂��ƂŎ��������ꍇ�������Ǝv����̂ŁA������g��Ȃ����Ƃ����B
�@�{���́A���������Ȃ���f�ڂ��Ă���̂ŁA�܂����������������������邪�A��e�͊肢�܂��B
���ӌ��E���₢���킹�����[���͂������
�������������� HOME��
-----�ҏW�ӔC�ҁF�� �T�� (Ji3CKA)-----
�@
�@